「ライフオーガナイザー」 初めて聞きます。って、言われることがあります。斯くいう私も、知らなかった一人です。
「整理収納アドバイザー」の勉強をして、技術的なノウハウを学んで。。上級クラスを目指す前に、整理収納を知るためにインターネット検索をしていたときに、偶然「日本ライフオーガナイザー協会」に辿り着きました。
「片づけ」 ≒ 「捨てる」
「断捨離」の本を読みました。この考えは、人生においては必要な場面がありますね。とても参考になりました。自分の生活をみると、ものが溢れて、処分しなくてはならないものがたくさんあります。
「処分しなくてはならないもの(捨てなくてはならないもの)」とは、他人が見れば、不用品や取るに足らない価値のないもののように見えて、本人にとっては思い出深い記念の品だったり、思い出深いものだったりします。
私が抱えているのは、まさに他人からみれば、不用品だけれど、私にとっては宝物です。旅先で見つけたポストカードや表紙が気に入って買った洋書だったり。。
なので、なかなか「捨てる」ことが出来ず、整理をするのに、悩んでいました。
「断捨離」での考え方は、捨てて、さらに捨てて、厳選したモノが残るという考え方です。
「離」モノへの執着から離れ、ゆとりある〝自在”の空間 (やましたひでこ著「新・片づけ術 断捨離」より)
そこまで到達するまでに悩み迷ってしまうのは、自分にとって思い出の品で、思い入れのこもったものだからでした。
何のために片付けるのかを考える・・・どうすることが自分にとって心地よいのだろうと考える・・・
オーガナイズするということ。
ライフオーガナイザーの考え方として、手元にたくさんある記念の品や思い出深いものを
小さな聖堂に見立て、選び抜いて飾ると言う捉え方があります。
部屋の中に、思い出コーナーを作り、そこにコンパクトに飾ってみます。
ただ、箱に仕舞われていた思い出の品も、目に触れることで、懐かしさやそのとき感じた嬉しさが蘇ってきます。
それを眺めることで、心が満たされたり落ち着いたりすると、小さな聖堂としての効果はあるのでしょうね。
思い出の象徴や代表するものが決まれば、残りは手放したり、処分をしようと思う気持ちが湧いてくることでしょう。
飾りたい。いつも見ていたい、。と感じるものが見つかれば、その他のものの役割(行き場)が見えてくるのではないかと思います。
使わないから捨てる。のは、作業として出来ますが、
愛着のあるもの、思い出のあるものは、その判断がとても難しいと思います。
私の寝室の書棚に、飾り棚のような空間を設けています。
そこに飾ってるのが、エッグアート「ピサンキーウクライナエッグ」です。このエッグアートは、思い出深いものです。
東日本大震災の折、都内で勤務中に被災したので、翌日帰宅した浦和の自宅も影響を受けていました。飾ってあったもうひとつのエッグアートは壊れてしまいましたが、この卵ちゃんは、箱に仕舞われていたことで、壊れずに残りました。
絵柄は「やどりぎ」です。
やどりぎは、なにやら よい意味があるみたいです。。
もうひとつの空間には、家族との思い出
猫のきゃりちゃんともぐちゃん。
レモンの土笛は長女の学生時代の学校の課題作品
(独り暮らしの私が埼玉から大阪に引っ越す荷物にあったのだから・・・よくこれを大事に仕舞っていたなーと我ながら感心します)
懐かしくて、きゅんとします。
長女が学生時代を送っていた頃を、思い出しますね。
ものは思い出や感情がこもっています。 手元に残す意味を味わって暮らしたいと改めて感じています。
手放すことと、手元に置いておきたい思い。。
自分のこれまでを振り返りながら、ものとの向き合い方などを一例として紹介していきたいと思います。

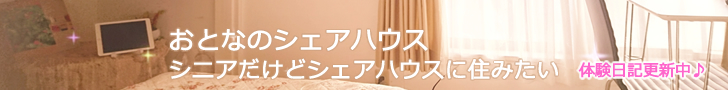


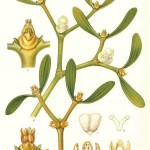


























 PAGE TOP
PAGE TOP